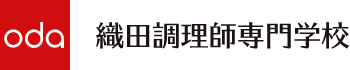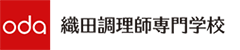日本の食文化にすっかり浸透した中国料理料理といえば、まず何を思い浮かべるでしょうか。
ラーメン?ギョウザ?
その中でも特に家庭で作る機会が多く馴染み深い定番メニューはチャーハン(炒飯)ではないでしょうか。
今回は単純に見えて奥が深いチャーハン(炒飯)をクローズアップしてみましょう。
チャーハン(炒飯)はもともと「砕金飯」という名称だった?

チャーハン(炒飯)の発祥には諸説ありますが、「砕金飯」という名で登場した説が有名です。卵に包まれたご飯粒を黄金のかけらに例えたものだと推察されているそうです。
家庭でのパラパラなチャーハン(炒飯)の作り方とは?味付けや調味料も確認
結論からいうと、家庭でもパラパラなチャーハン(炒飯)を作れます。
まずは、フライパンをしっかりと熱しましょう。軽く煙が出るくらいまでしっかりと熱してから油を入れてください。カロリーが気になるかもしれませんが、油はあまりケチってはなりません。
油の代わりにマヨネーズを使用しても味付けにコクが出るためおすすめです。
卵の投入方法に関してはさまざまなレシピがあります。お米一粒一粒を卵がきっちりコーティングしてくれているチャーハン(炒飯)が好みなら、あらかじめご飯と卵を混ぜておいてフライパンへ投入するのが簡単です。
対して卵の食感がある程度出るほうが好みなら、熱々のフライパンへ卵を割り入れ、まだ固まらないうちに卵の上へご飯を投入しましょう。お玉の底を使い、卵へ押し付けるようにしてご飯の塊を砕きつつ卵と混ぜるようにします。
この方法ではご飯が卵でコーティングされつつも卵の塊で食感を出すことができます。


そして最後のポイントです。味付けに醤油を使う場合は特に、ご飯へ直接かけないようにしましょう。せっかく水分を飛ばしたのに、調味料の水分をご飯が吸ってしまってはなりません。ご飯を寄せてスペースを作り、回しかけるように投入します。
ぜひ自宅でもパラパラでおいしいあのチャーハン(炒飯)を楽しんでみてください。
織田調理師専門学校では……
織田調理師専門学校の「調理技術経営学科」では中国料理だけでなく、西洋・日本・デザートなど多岐に渡る調理方法を、2年間かけてじっくり学ぶことができます。
進路の上でも、学生一人ひとりの将来の方向性に沿った就職アドバイスをし、夢の実現を強力にサポートしています。